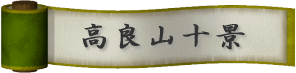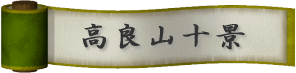竹楼の春望
妙法院宮二品法親王尭恕
竹楼百尺青穹に傍ふ 万里の山川目力窮す
柳色淡濃花遠近 一望処として春風ならざるはなし

楼の上は 春こそことに くれ竹の 世のつねならず 霞むうみ山
源寂
竹を葺く小楼半穹に聳ゆ 短簷景を聚めて興窮り無し
春来添へ得たり六宜の外 万里の山川柳の風
永き日も 詠めにあかず くれ竹の よにたぐひなき 楼のをちこち
吉見の満花
転法輪大納言実道
一嶽峻険として九天に聳ゆ 桜花四に発して更に嬋娟
径に芳野を移して春色を添ふ 圧倒し華山玉井の蓮
今出川内大臣公規
あかず見む よしみが嶽の 花盛り わきてことなる 春の色香を
源寂
最も愛す吉峯三月の天 山桜笑を含んで玉嬋娟
吾盧今衆香界に接す 転た憶ふ遠公の白蓮を結ぶことを
咲花の よしみがたけや 三芳野の 春におとらぬ さかりみすらむ
御手洗の蛍
柳原大納言資行
玉垂在昔斯水に臨む 神迹芳を流す橋上の名
御手洗の余滴散るかと疑ふ 光を凝し矜り照して宵行を作す
日野中納言弘資
くるゝ夜は ほたる涼しく 河風に みだれ橋てふ名も朽ずして
源寂
千古の霊神垂降の日 渓流手洗小橋の名
丹良今昏衢の燭を秉て 山僧に分与し夜を照て行しむ
暮るゝより 蛍涼しく みだれ橋の した行く水に かげをうつして
朝妻の清泉
高辻中納言豊長
朝妻の風景尽く新奇 松緑に杉青して四時に伴ふ
湧出す清泉林岳の下 霊蹤雄地総て相宜し
園大納言基福
汲みてしる 心も清し 神わざも 代々にたえせぬ 朝妻の水
源寂
神功の垂跡地尤も奇なり 混々たる琴泉尽くる時無し
遊客帰を忘る三伏の日 流を枕とし石に嗽いで両相宜し
朝づまの 清き流に すゞぎても にごる心は すむとしもなし
青天の秋月
花山右大将定誠
寺は青天と称す青嶂の頭 高低一望点塵収まる
啼猿樹上深秋の月 特り行人万里の愁を照らす
中院大納言通茂
寺の名を 月にもしれと 秋風や あゐより青き 空にすむらん
源寂
青天の蘭若一峯頭 月は碧松を浸して烟霧収る
昼夜眠らず玉壷の裏 西欄影落て人をして愁へしむ
雪はみな 払ひつくして 秋風に 青き天行く つきのさやけさ
中谷の紅葉
柳原侍従秀光
青女染成す日夜の功 満山処として霜楓ならざるはなし
疑う瀑布千尋の白きを将て 変じて秋梢一様の紅と作すかと
日野中納言資茂
秋をしる 色もみえけり 松竹は ときはの中の 谷のもみじ葉
源寂
山間の秋景天功を見る 飛瀑高く懸て岸に酒ぐ
風後一泓中谷の水 玻璃盆裏猩紅を貯ふ
滝の糸に もみじの錦 おりはへて あらふと見ゆる 中谷のみづ
不濡山の驟雨
伏原少納言宣幸
朔風吹散す濡せぬ山 幾度は変す浮雲頃刻の間
是れ紫陽奇絶の処なるべし 晴と作り雨と作て転た清閑
阿野中納言季信
この比は なのみねれぬ 山姫の 袖もほしあへず ふる時雨かな
源寂
盧を結んで我を置く不濡の山 液雨陰晴丘壑の間
雲去り雲来る空洞裏 無心更に老僧の閑に伴ふ
風にさる 峯の木の葉の 時雨には さらにぬれせぬ山かづの袖
鷲尾の素雪
東園宰相基量
勝処従来名自ら伝ふ 時に景物を添えて更に憐れむべし
何人の詩思か銀海を揺す 鷲尾峯頭雪後の天
烏丸大納言光雄
積りそふ 雪の日数を 重ねあげて いとゞうへ見ぬ 鷲の尾のみね
高隆の晩鐘
勘解由小路従四位下侍従韶光
樹老い径荒れて煙水清し 高隆の遺跡昔年の名
唯今猶鐘楼の在る有り 扣出」す黄昏三両声
平松中納言時量
山高み たかき甍は いるくもの そことしらする 入相のかね
源寂
高隆の遺跡蘚苔清し 境は詩章に入て再び名を播す
一杵の楼鐘山樹の裏 両三驚和す晩鴉の声
かげ高く 隆ぶる寺の木の間より 響き出たる いりあいのかね
玉垂の古松
竹内二品法親王
瑞玉垂れ伝ふ 古廟宮 威霊在すが如く今に至って同じ
老松風度りて神曲を起す 盛徳遺音瞻仰の中
白川二位雅喬
末たかき 松やしる人 玉たれの 宮居久しきむかしがたりを
源寂
洪基年久し玉垂の宮 国鎮巍々として今古同じ
更に長松天籟の韻を借りて 三たび万歳を叫ぶ白雲の中
十がえりの 花も幾たび 契りてか 松もとしふる 玉たれのかみ
|