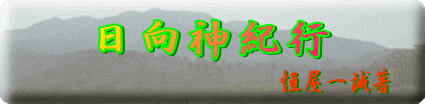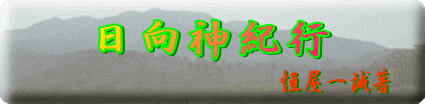夫より矢部村に入り、宮野に至れは、人家相連り、呉服屋あり酒屋あり族亭あり、得業士の医師も見受けたり、今日は決して酒屋三里豆腐屋一里的の矢部に非ず。当所より左に折れ行く程に、向う岸に百日紅の映き乱れけれは、
來て見れは 青葉かくれに 紅の
百日もにほふ 花咲にけり
來城日。 風致婿然、亦所謂万緑叢中紅一点なる者。
一里半程にして北御側に至り、後征西将軍の御墓に参拝したるは、点灯の頃なりき、転た懐旧の情に堪えず
ぬかつきて 袂しぼらぬ 人もなし
大杣の宮の そのあとゝころ
藤本雲外
山腹一杯の土、曽て埋む帝子の魂、吾れ來って往事を懐えば、暗涙黄昏に灑ぐ
來城曰。 所謂蒼茫独立之境,覚えず万感何れの処従り來
又、三水の井あり、土人伝へて言う、将軍毎晨盥嗽の所なりo
心して汲めや山人古への
これそみもひの八女のいさら井
藤本雲外
廟側牛泓の水、寒光明鏡開、之を臨めば敬慕を増す、曽て玉姿を照らし來、
師富藍谷
青苔陵上に盈つ 古木英魂を護す
豈古昔の感無らん 佇立黄昏に到る
陵下清水有り 宛も明鏡の開くが如し
盥嗽人已に去り 玉葉眼を照らし來る
沼北曰。 征西軍逐に振わず、英霊長く此地に留む、一杯の土纔に存す、而御前嶽御側名之尊禰古跡、口碑に存する者、千古朽ちず、民心感戴の深き知るべし、突、予亦嘗御陵墓を拝するの詩三絶有り、其の一曰く、
渓流箭の如く石刀の如し 颯颯たる西風万籟号ぶ、
千古遺跡一杯土 白雲奮に依って洞門高し、
不覚暗涙数行下る、聞けは此庭を過るものにして、或は一点の涙をさへ浮べざるものありと、人心の腐敗も亦甚哉。木賃宿江田萬吉宅に一泊し、種々往時よりの事とも聞き質したるに、朴訥なる田舎男の話しに、思はす疲労を忘れて夜を更しぬ。
つくろはぬ昔語りに山人の
直く正しき心をそ知る
又特に感せしは、席に侍せし少婦に年歯を問うに、同行の推測より一歳を加うと、明らさまに答えたること是なり、婦人は概して年を秘するものなるに、彼の少婦か天真燗漫人を欺かさるの美質賞すべき哉。
かさりなき里ひ少女か言の葉に
心のおくの花そにほへる
雲外日。亡父復云、
かさらはぬ里ひ処女の言の葉の
根さしは深きまことなりけり
藤本雲外
世上滔々の女、巧言人を魅せんと欲す、山娘淳愛す可し一語真情を見る
來城日。此所謂三逕式也、何ぞ其の些事に感する之甚耶。
夜更けて枕に就きたれども、蚤虫多く襲ひ來りて眠る能はず、只ふらふらと夜を明したるのみ。翌朝雨止まず、前夜山賎の話に、日田まで六里とあり、同行皆曰く彼地に足を転するも亦一興ならんと、直に日田行に決す。主人曰く今は蛇蝮路に横はり、其上草木生い茂り路と云ふへき路もなく、険わしき三里ばかりの山越なれは、如何なる壮士も越えがたからんと、皆曰く何ぞ都人の儒風を学ばん、人間何事か成し難からんと、勇を鼓して発足す。路に女郎花の咲き乱れたるを見る。
世に遠き 八女の山路の 女郎花
たれに心を よせて咲くらん
露深みに ほふ行手の 女郎花
誰にをれとか さき匂ふらん
來城日。 余嘗御側従り日田に赴く。道を失い熊渡に入。日暮れ東西を弁ぜず、遂に渓間に宿す。。秋気水の如く肌に沁み眠る能わず、平明旧路を取り帰る。今之を憶えば恍として隔世の如し。
欝蒼たる大木の道を遮きるあり、幽谷あり独木橋の架するあり、跋渉頗る難し。加之猛雨沸然として下り、怪雲四方に塞りて、四顧冥々たれども好奇の心は我をして羽化登仙の想を成さしめつゝ、三里の峻坂も無事に越え終りて、日田郡田代村に抵るo
ふりすさふ雨にさはらて三沼人
こえこそわたれ日田の山里
雲外曰。予亦風雨之日、御前絶巓に立つ怪雲四もに塞り乾坤空濛、寸物の眼を遮る無し紳魂瓢忽、真に羽化登仙の想い有り。読んで此間に至りて、当時を回想すれば覚えず魂動く。
来城曰。杜甫句に云う、峯参兄弟皆奇を好む、諸君亦其の一輩流歟。
時已に正午なり、一渓の農家に休憩し、午飯を喫す。紫電一閃、叉もや一大雷雨の至るあり、耳聾し、目眩し、心胆をして夏猶寒からしむ。須臾にして天晴れ雨も休みけれは、日田に向つて発足す。從是高瀬川に沿うて下るに、水溢れて之に架したる橋梁も、夜來の暴雨に流決し、大に行路の人を悩ましたり。行くこ三二里許にして渓間を出て、稍々広き田野に出づ。日己に傾く、何処の寺にやあらん、晩鐘を送りぬo
族人の 淋しさ添へて 響くなり
とほ山寺の 入相の鐘
藤本雲外
鐘声何れの処の寺、一杵黄昏を促す、是れ遠路の客ならず、他郷断魂し易し。
次韻師富蘆谷
薄暮山谷を辞す、匇匇行路昏し、更に又た鐘響を添う、凄然旅魂を驚かす。
来城曰。 筆々頓挫、真に愛誦す可し。
斯ぐて目的地たる日田の荘にそ着きにける。四面皆山なり、其風其趣文人墨客の出つるも、亦た其の地形の然らしむる所ならんと、互に打語りつゝ先づ隈町を通過し、豆田町に至り、昔時の代官所跡、並に廣瀬淡窓翁の成宜園を訪う。園は豆田町の外れにあり、跡に郡衙あり、校舎あり、或は桑田に化しつゝあり、翁の邸宅は今猶存すれども、簷傾き垣破れ復旧観を留めず、庭前の老松独り翁の遺訓を呵護するものゝ如し。中に二三の児童か(口尹)唔の声を聞く、何となく過し昔の偲ばれて感慨多少。
來城曰。 荒景を写し來感慨其の中に在り、読者神を傷む。
沼北曰。 成宜園の天下に鳴る、淡窓門下の士、高材碩徳亦不其の人に乏しからず也、後人翁の徳を追慕し、翁の遺跡に恋々たる也亦宜なり。予後生翁に親炙を得ずと雖も、笈を宜園門下に負う、私淑する所有り。今此の記を読み敢えて所感を付記す也。
夫より隈町に引返し、古後なる旅亭に投す。時已に点灯の候なり、亭は屈指の旅亭にして、前夜の旅亭に比すれは、其の差恰も白屋の甲第に於けるが如し。今夜こそ思う侭に気炎を吐かんと、第一着に酒を命ず、一杯一杯、酒亦口に適せり。一人曰く是れ田舎の酒に非ずと、侍者答て曰く、城嶋附近の酒なりと、余嘆して曰く、鳴呼三潴は人物を以て世間に鳴る能はず、責めて酒もて世間に鳴るを得ば、幾分肩を張るを得べしと、衆皆口を開いて大に笑う。膳に上る下物は名産の香魚なり、塩焼或は鱠にして美味言う可からず。殊に旅亭は隈川に臨み、西岸は高瀬とて一小部落をなす、燈火の水に映し、金波の動揺する景色実に賛美の辞なし。棲下忽ち声あり、回顧すれは一葉の扁舟下流より上り来て網を投ずるあり.細鱗溌剌として躍る。又対岸に牛を放つの翁あり、牛は意の欲する所に随つて芻秣を食う、其の趣其の状誠に仙境にある心地しぬ。抑々此の行山中一日の好天気なく、雨又雨にて、深山幽谷を跋渉したるも、存外疲労を覚えず、三人共多少健脚を以て自ら誇れり、今一泊と思へごも、同行に帰りを急ぐ人あり、遂に舟を買うて浮羽郡山春村荒瀬に上陸す。途中には随分危険のの急湍あり、文政の当時、頼翁之を下りて水流箭の如く万雷吼ゆと云いしは、真に我を欺かず。吉井田主丸を通過し、大橋より更に舟を雇いい宮地に上陸す。時己に夕陽西山に舂く頃なりき、即ち米城にて一酌を試み夜家に帰る。
師寅蘆谷曰く。 三瀦の酒、醇乎として醇夷、故に其の名夙に天下に著る、然して其の著る所以の者、自ら鳴く也。古人曰く、十室の邑、必忠臣有り、三瀦の地数万、豈人才無からん哉、其の著れざる則て鳴かざる所以也、諸君今將に鳴かんとす其の著るるや必せり、何ぞ人才無きを傷まん。
藤本雲外曰く。 三瀦の酒天下の醇、醸す所幾万、穀を消す幾億、三瀦の精粋酒に依って尽く、英霊漢出ざる所以か。一たび此霊液を嘗めんか、老者は壮、天者は寿、憊者は健、懦者は奮、鼓活動して天下の人動於天下之人心を舞い己まず。其の徳亦偉ならず。
星野沼北曰く。 隈の客舎山紫水明の間に在り、鮮を割き飲を侑む何の快か之に如かん。舟隈川を下り荒瀬に到る、此の間亦一奇勝。文中縷縷記之を記す、筆端自ら畳y煙霞の気有るを覚ゆ。
宮崎来城曰く。 日田の風景、余之を聞く已に久し、而未だ嘗て一遊せず。今高文を読み、山光水色紙上に縦横し、美酒佳肴、筆下に羅列す、人をして恍然身を其の境に置くの想い有らしむ也。余爲に半日の臥遊を喜ぶ。
|